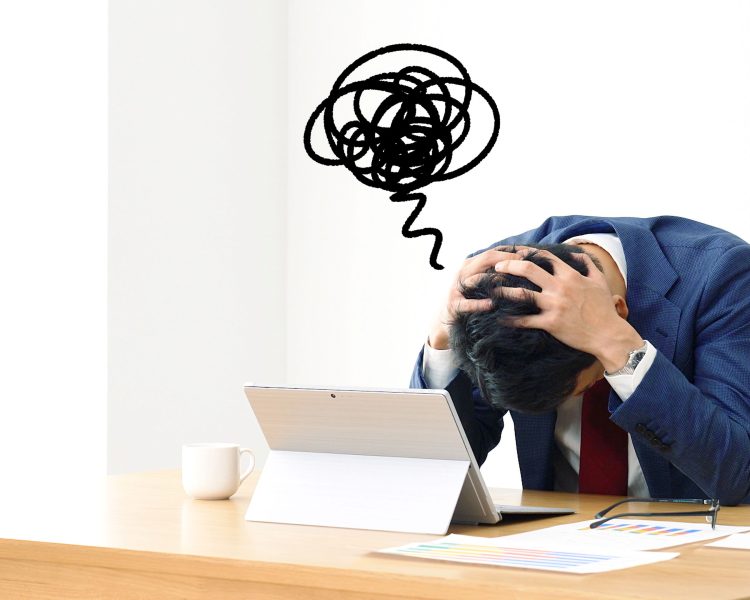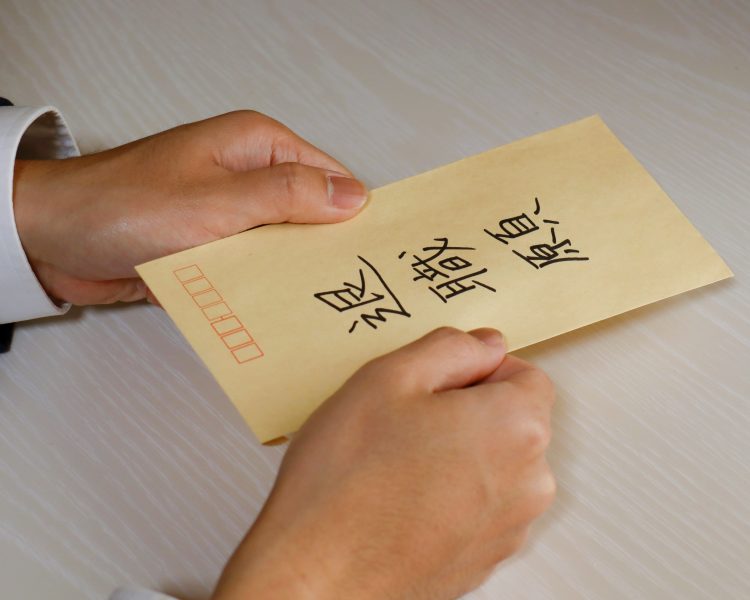請求書の再発行依頼が来たらどうする?正しい対応方法とリスク回避策2025.10.09

請求書の再発行依頼、続いていませんか?取引先からの再発行依頼は、相手の都合によることもあれば、こちら側のミスが原因の場合もあります。いずれにしても、同じ作業を二度繰り返すのは避けたいですよね。
再発行が頻発すれば、取引先からの信頼を失いかねません。原因やリスクをしっかりと把握して、対策していきましょう。
今回は、請求書再発行時の正しい手順と注意点、そして再発行そのものをなくすための根本的なポイントを解説します。
【この記事の監修者】 株式会社Bricks&UK Outsourcing業務コンサルタント
経理の業務設計・運用に優れたコンサルタントが、効率的で正確な業務請負いをお約束します。
目次
請求書再発行の正しい手順
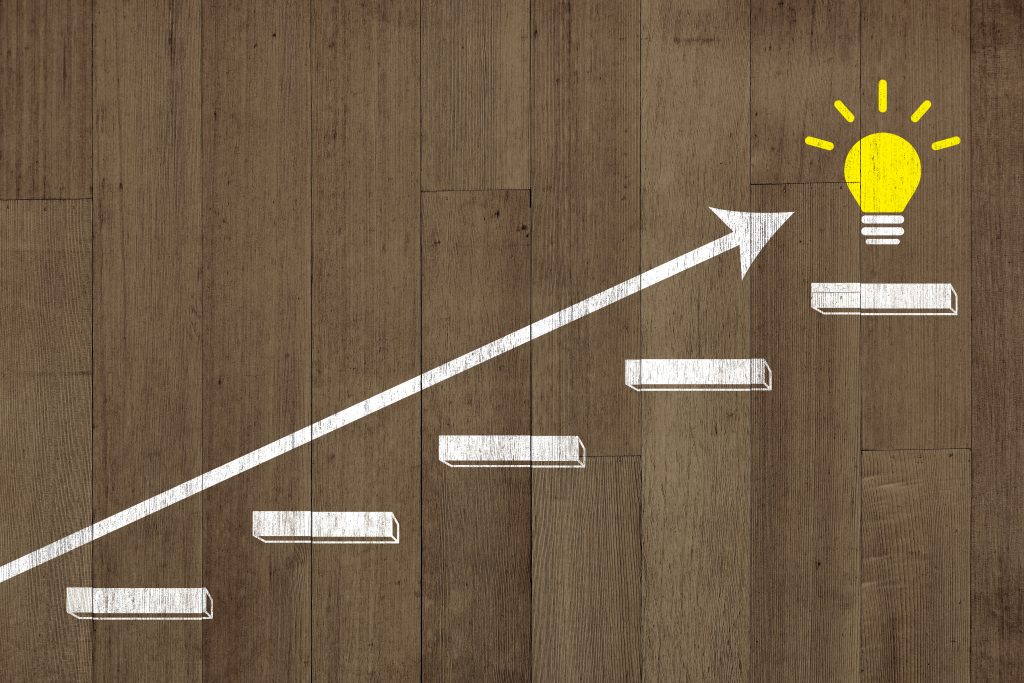
クライアントから「請求書を再発行してほしい」との依頼が届いたら、慎重に対応しましょう。
再発行する前に、まずは確認事項があります。順に説明します。
1)依頼内容と理由の確認

どの請求書に再発行が必要なのか、まずはその発行日や請求金額、請求書番号などを確認しましょう。
このとき、「なぜ再発行が必要なのか」の理由も確認してください。こちら側にミスなどの落ち度があった場合には、確認後すみやかに謝罪する必要もあります。
請求書に間違いがあった場合の、謝罪などの対処法については、こちらのコラムで解説しています。
2)請求書の再発行
依頼されたとおりに、請求書を再発行します。この時、再発行したことが一目でわかるよう、「再発行」と記載しておきます。記載する位置は、請求書番号の横など、上部の目立つところが最適です。
作成したら、記載内容に間違いがないか、一字一句確認してください。
3)再発行した請求書の送付

再発行した請求書を、取引先に送ります。
送付状やメールには、「〇月○日付けの請求書を再発行いたしました」などの一言を必ず添えましょう。こちらの落ち度による再発行の場合は、その前に丁寧な謝罪文を送るのが礼儀です。
請求書再発行時に注意すべき5つのリスク

請求書の再発行は、作業として難しいものではありません。しかし対応を誤ると、信頼の失墜や法令違反によるペナルティにつながる可能性も。ここでは、再発行時に特に注意すべき5つのリスクについて解説します。
二重請求・二重支払いのリスク
再発行した請求書が、相手先にも「再発行したものである」と認識されなければ、二重に請求したと見なされるリスク、二重に支払われてしまうリスクがあります。
二重に支払われれば、振込手数料の負担や返金手続きの手間など、相手に余計な負担をかけることとなり、自社の信頼も大きく損ねます。
再発行の際は、請求書に「再発行」と明記し、メールや送付状にも必ずその旨を記載しましょう。また、請求書番号に枝番(123-A、など)をつけるのもおすすめです。
経理上の二重計上のリスク
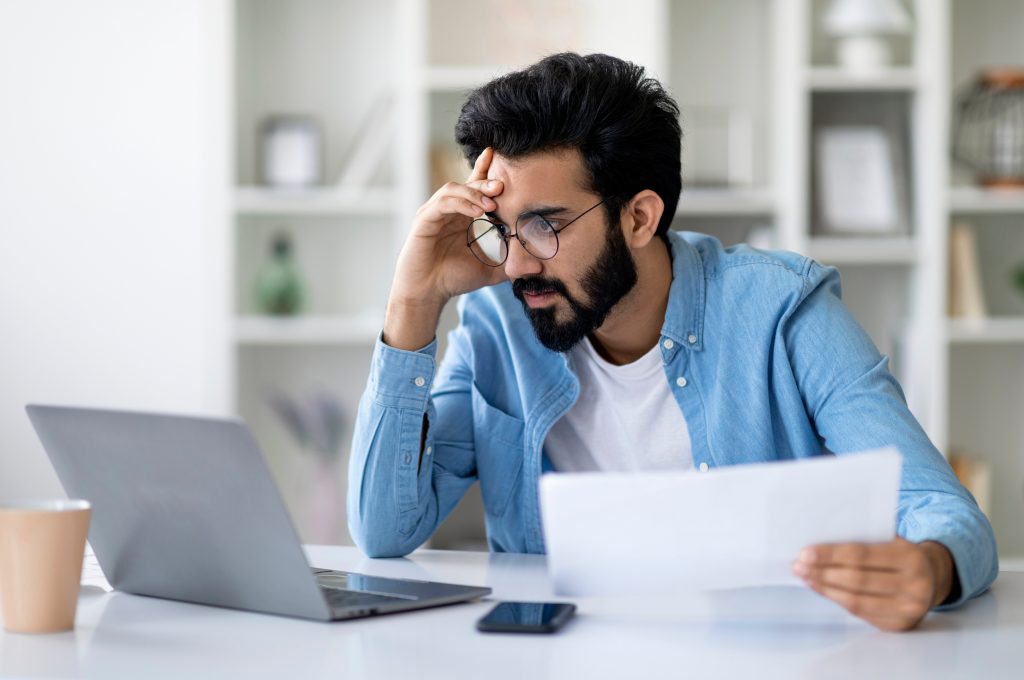
再発行には、再発行と元の請求書、両方を売上に計上してしまう「二重計上」のリスクもあります。
これは帳簿の不備となるため、税務調査で過少申告を疑われたり、追徴課税の対象となったりする恐れがあります。
元の請求書の控えは必ず、再発行した請求書とセットにして保管・管理してください。再発行の記録(依頼日や理由など)もあわせて残しておくと安心です。
税法上の保存義務違反のリスク
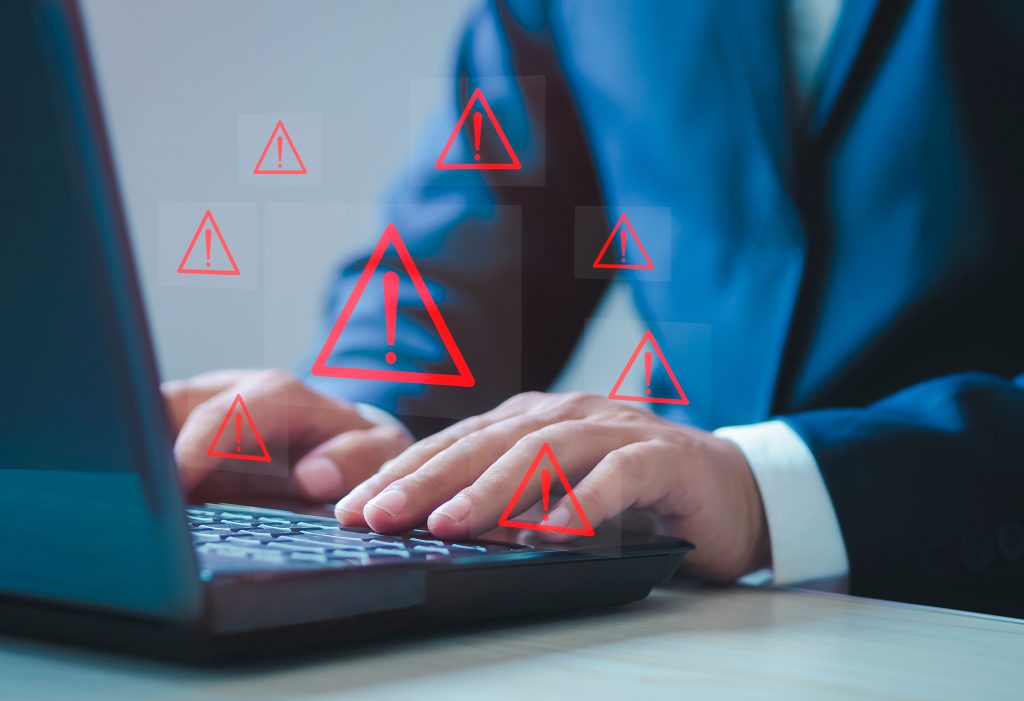
再発行したからと言って、元の請求書を破棄してしまうと、法令違反となるリスクがあります。請求書は、法人税法や消費税法で7年間の保存が義務付けられている重要な証憑だからです。
元の請求書がないことにより、税務調査で正当な取引だと認められなければ、仕入税額控除が受けられなくなる恐れが。帳簿の信頼性もないと見なされれば、追徴課税などの対象ともなり得ます。
元の請求書は必ず取っておきましょう。
業務効率が低下するリスク
再発行が頻繁に発生すれば、確認から再発行、紙であれば印刷や郵送など、無駄な手間と時間がかかります。
とはいえ、慎重に進めないとさらなるミスにもつながり、より集中すべきコア業務の遅れ、さらには社内全体の生産性が低下することに。
再発行の必要性が何度も生じる場合には、原因を特定し、早急に解消しなくてはなりません。
取引先からの信頼を失うリスク

自社に原因がある請求書の再発行を繰り返していると、取引先からの信頼を失います。
「管理体制がずさんなのでは」「能力的に問題が?」などと疑われてしまえば、信頼に足る企業かどうか、という点で、本業の取引自体にも懸念が生まれてしまいます。
謝罪やその後のフォローなどもしっかりと行うことが重要です。改善した点なども伝えておくとよいでしょう。
再発行が必要となる3つの根本原因
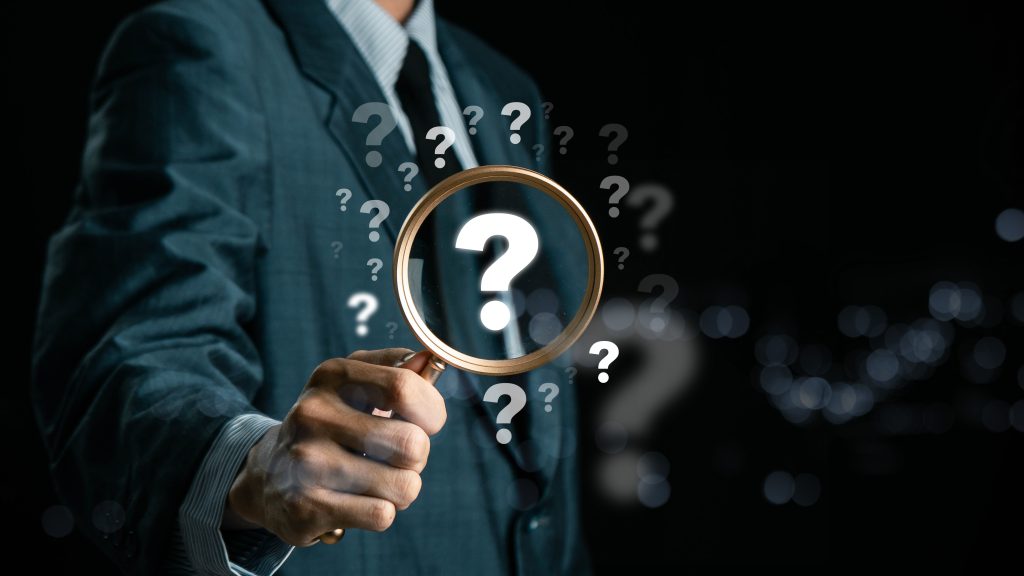
請求書の再発行は、単に「相手が紛失した」「金額を間違えた」という表面的なことだけでなく、体制などに問題はないかを確認し、原因を突き止めて再発を防ぐ必要があります。
よくある原因として挙げられるのが、次の3つです。
- 紙などによるアナログな管理
- 業務の属人化
- 確認フローの不備
順に説明します。
紙などによるアナログ管理
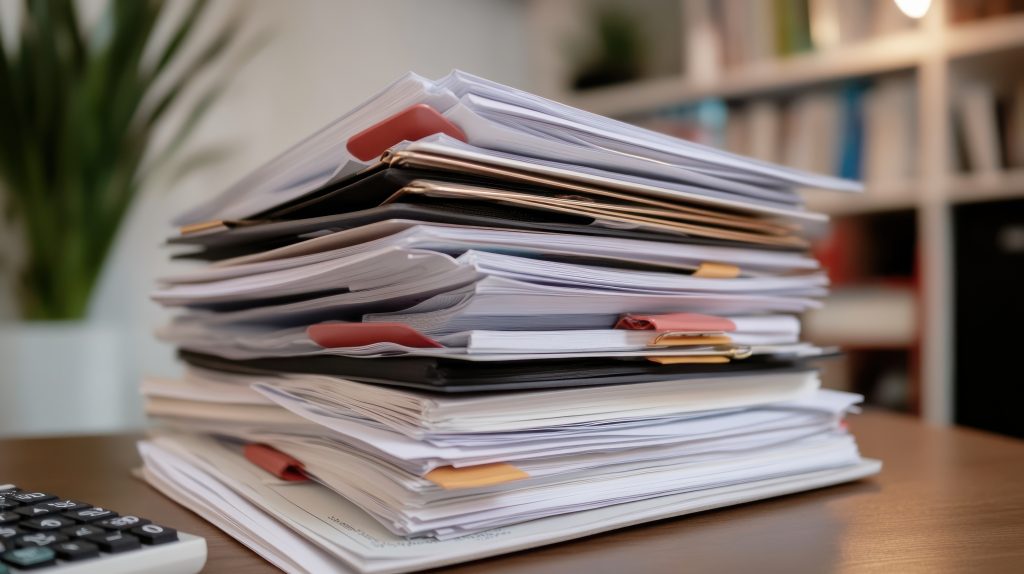
請求書の作成や管理を、紙やExcelなどのアナログな方法で行うのには、ミスを起こす大きなリスクがあります。
手作業ではどうしても、宛名の記載ミス、金額の転記ミス、計算間違いといった単純なミスを起こしやすいからです。
また、再発行時の対応にも時間がかかりがち。過去の請求書データを一元管理できず、請求書をいつ誰に送付したかなど、履歴の追跡にも時間と手間がかかります。
業務の属人化

経理では、業務の属人化も大きなリスクです。
たとえば、担当者が休みなどでいない時。急な請求書発行依頼には、慣れない別の社員が対応しなくてはなりません。ルールや業務手順が共有されておらず、自己流で作成してしまうと、記載漏れや間違いにつながります。
通常と異なる作業なので、ミスも起きやすい状況ですし、再発行の依頼を受けた際に担当者が不在の場合、さらなるミスにつながりかねません。
確認フローの不備
請求書の発行時、送付前のチェック体制が整っていないことも、再発行につながるミスの原因です。
請求書は、社外向けの重要書類です。送付前には金額や宛先、口座内容などをしっかりと確認すべきであり、チェック体制がなければ、ミスは何度でも起こる可能性があります。
再発行のリスクやストレスから解放されるには

請求書の作成時にかかる上記のようなリスクを排除しなくては、再発行のリスクや、その手間によるストレスはいつまで経っても解消されません。
すぐにでも着手すべきおすすめの解決策は、次の2つです。
- クラウド請求書システムを導入する
- 経理アウトソーシングを利用する
それぞれ解説します。
クラウド請求書システムを導入する

クラウド請求書システムとは、オンライン上で請求書の発行から送付、管理まで一元化できるシステムのこと。再発行につながるミスを大幅に減らせ、次のようなメリットもあります。
- ヒューマンエラーの防止
- 属人化の解消
- 履歴の明確化
ヒューマンエラーの防止
システムを使えば、計算が自動でできたり、請求書番号が自動で付与されたり、過去のデータを活用できたりするので、手作業によるミスが減らせます。
属人化の解消
また、システムで情報共有をし、業務を標準化しておけば、誰にでも簡単に請求書発行を行えるようになります。担当者がいなくて困ったり、その他の業務が滞ったりするようなことはありません。
履歴の明確化
システムなら、誰がいつどの請求書を発行したのかの履歴が残るのも大きなポイント。膨大な書類から1枚1枚見て探す必要がありません。
問い合わせが来たときの確認や、もしもの再発行時もスムーズに対応できます。
経理アウトソーシングを活用する

「自社に合ったシステムの選定や導入をしたいけど、手間も省きたい」という場合は、専門業者に代行してもらう「アウトソーシング」が有力な選択肢となります。
経理アウトソーシングなら、請求書発行業務だけでも、経理業務まるごとでも委託可能。自社負担は大幅に減ります。次のように大きなメリットもあります。
- トータルコストの削減
- 本質的な課題の解決
- コア業務にあてる時間の確保
- 専門家による業務の安心感
トータルコストの削減
アウトソーシングに依頼することで、経理担当者の人件費(給与・社会保険料・福利厚生費など)のほか、備品やソフトウェア、教育費などの間接的なコストも大幅に削減できます。ミスによる金銭的コストの確率も低くなります。
本質的な課題の解決
再発行が起きる原因であるアナログ管理や属人化が一気に解消できます。業務フローの改善も行ってくれる業者が多く、ITソフト導入についてもアドバイスが得られるため、根本的な問題の解決に役立ちます。
コア業務にあてる時間の確保
請求書発行にかかる時間、もしくは経理作業にかかる時間がなくなれば、売上に直結するコア業務に専念できます。結果として、会社の増益や競争力の強化が期待できます。
専門家による業務の安心感
経理アウトソーシングは経理を専門に代行する業者なので、ミスの可能性も低く、税法の改正時にも即対応が可能。法令違反のリスクからも解放されます。
請求書再発行も経理アウトソーシングにおまかせ

請求書の再発行は、それ自体が信頼を失いかねないだけでなく、対応のミスによってさらに大きなリスクを引き起こします。最悪の場合、取引を打ち切られることも。
再発行がひんぱんに起きているようなら、根本原因を突き止めましょう。解消する手段としてシステムの導入と経理アウトソーシングの活用を挙げましたが、より効果的なのは経理アウトソーシングでプロに代行してもらうことです。
当社「Bricks&UKアウトソーシング」では、業務フローの設計に長けた担当者が丁寧にヒアリングを行い、最適な経理環境を構築します。税理士法人を母体としているため、会計や税務関連についてもお手伝いできます。お気軽にご相談ください。