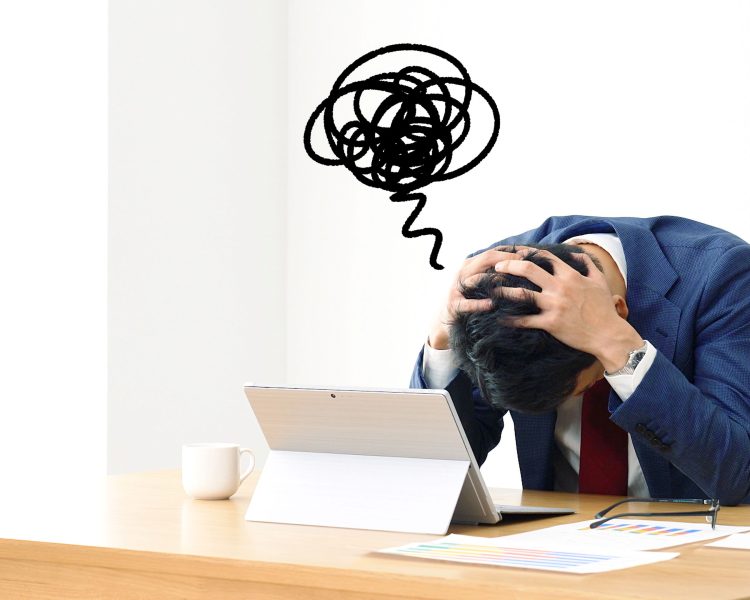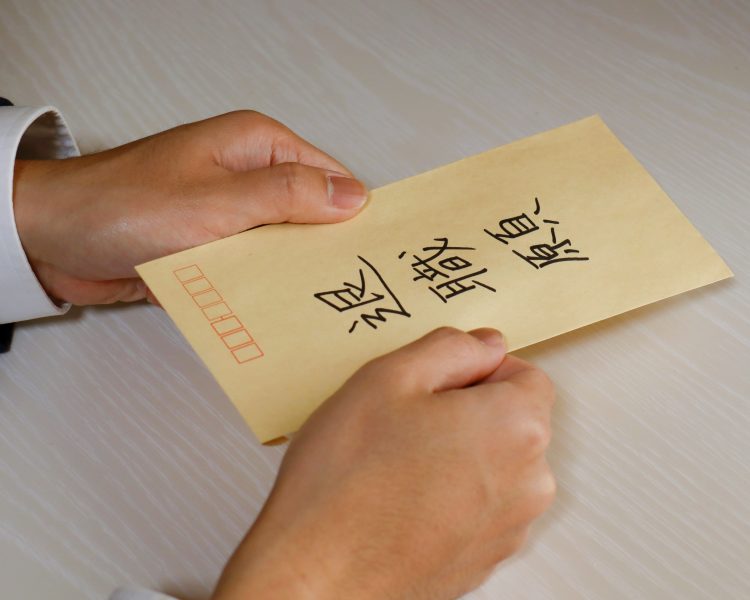事務代行に委託できる業務とは?サービスの種類やメリット、選び方を解説2025.03.25

「日々の業務が忙しく、事務作業まで追いつかない」「社内に事務ができる人がいない」「求人募集をする余裕もない」…。そんな個人事業主や中小企業をサポートするのが、事務代行サービスです。
今回は、事務代行サービスとはどんなものか、委託できる業務の内容やサービスの種類、メリット・デメリットなどを解説します。
代行業者の選び方や、業種別の活用事例も紹介するので参考にしてください。
【この記事の監修者】 株式会社Bricks&UK Outsourcing業務コンサルタント
経理の業務設計・運用に優れたコンサルタントが、効率的で正確な業務請負いをお約束します。
目次
事務代行サービスとは
事務代行とは、企業や個人が事業を行う上で必要となる事務的な作業(主に机の上で行う書類やデータ作成など)を代行するサービスや、その代行業者を指します。
事務の仕事が多岐にわたるのと同じく、事務代行のサービス内容やサービス形態には複数の種類があります。まずはその種類を把握しておきましょう。
事務代行サービスの種類

事務代行サービスには、主に次のような種類があります。
| 事務代行の種類 | 代行サービスの内容 |
|---|---|
| 一般事務 | 文書作成、データ入力・チェックなど |
| 総務事務 | 電話・メール対応、スケジュール管理など |
| 経理事務 | 記帳、請求書発行、支払処理、給与計算など |
| 営業事務 | 資料作成、見積書作成、名刺のデータ化、在庫管理、顧客管理など |
| 人事・労務 | 採用活動、教育研修、人事評価制度の構築、入退社手続きなど |
それぞれの項目に特化して請け負う業者もあれば、「事務代行」としてまとめて請け負う業者、秘書業務やweb制作やSNS運用などを合わせて請け負う業者など、さまざまな種類があります。
事務代行サービスの形態

事務代行サービスをどのように行うか、その形態には主に2つあります。
- インターネット上で完結する「オンライン」
- 書類や物の現物を扱う「オフライン」
事務代行サービスでは、ほとんどの場合、パソコンを使ったオンラインで業務を行います。データなどを送付すると、代行業者のスタッフが代行業者のオフィスで作業してくれる形です。
中にはオフラインでの作業も請け負うところがあります。たとえば、代行業者に名刺や請求書を送り、ファイリングしてもらう、商品の発送作業をしてもらう、といった内容です。
オフラインには、代行業者のスタッフが委託元に出向いて作業をするパターンもあります。
事務代行サービスの料金体系と料金相場
依頼するにあたって、最も気になるのが料金です。料金体系と相場を見てみましょう。
事務代行の料金体系

事務代行サービスの料金は、業者あるいは委託する業務などによって体系が異なります。
主なものは次の3つです。
- 時間料金制…料金区分が時間区分で設定されている
- 月額固定制…毎月決まった料金を支払う
- 従量課金制…業務量に比例して料金が高くなる
※代行業者がこのような名称を使っているわけではなく、あくまで説明のため区分化しています
この他、クライアントの状況に応じたカスタム料金設定を行う業者もあります。また、専属アシスタントが付くかどうかで料金が異なるケースや、ひと月の稼働時間数によって料金区分を変えているケースも。
急ぎの納期など、オプション料金が設定されていることも多いです。
たとえば業務量が常に多い場合や継続して依頼する場合は、月額固定制が適しています。取引量が少なかったり、繁閑の差が大きかったりする場合は、従量課金制が効率的でしょう。
時間料金制は、スポットといってその都度依頼する場合や、一部業務のみを依頼する場合などに便利な料金設定です。
変動制は、専属アシスタントにするかどうかや、専門的スキルの必要性、ひと月の稼働時間などによって金額が変わります。
事務代行の料金相場

気になる料金相場についても、大まかに紹介します。
| 料金体系 | 料金相場 |
|---|---|
| 時間制 | 1時間あたり2,000円~5,000円 |
| 月額固定制 | 月額5万円~15万円(20時間~50時間) |
| 従量課金制 | 書類作成1件1,500円 データ入力1項目5円~ メール送信1件100円~400円 など |
これはあくまで相場であり、実際には業務内容や量、難易度や契約期間など、さまざまな条件によって大きく異なります。参考程度にしてください。
事務代行サービスを利用するメリット

事務を代行業者に委託することには、次のようなメリットがあります。
- コストを削減できる
- 業務効率化が図れる
- 業者の専門性を自社に活かせる
- 人手不足が解消できる
- 労務管理なども不要である
それぞれ説明します。
コストを削減できる

事務代行を利用するメリットの1つが、コストの削減です。従業員を1人雇うとしたら、求人広告料や人材紹介会社への手数料などの採用コストが発生するほか、給与などの人件費、パソコンなどの備品代から教育訓練費、光熱費などさまざまな費用がかかります。
事務代行に委託すれば、それらの費用はすべて必要ありません。
業務効率化が図れる

事務代行サービスを自社でサポートが必要な部分に適切に使えば、業務が大幅に効率化できます。社内での業務量が減るほか、業務プロセスの見直しも可能です。
事務専門の業者、第三者だからこそ見える改善点や、他社だからこそ指摘できる点もあるはずです。
業者の専門性を自社に活かせる
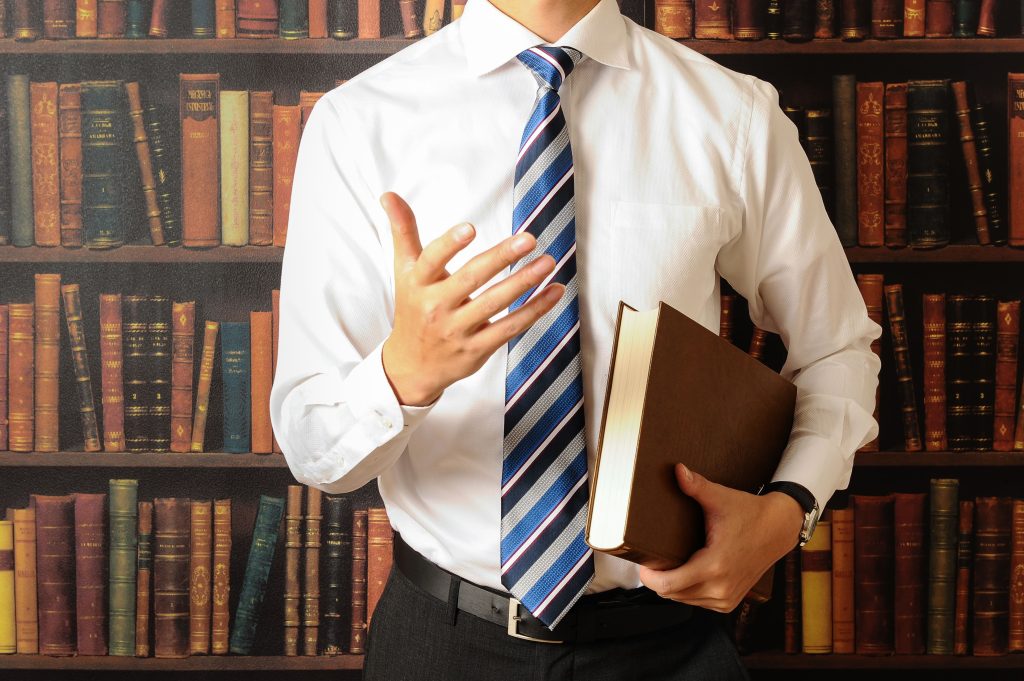
事務代行サービスのスタッフは、事務経験や知識を持つ人ばかりです。最新の法改正や制度変更などの情報もスピーディーにキャッチして対応してくれます。
最新のITツールやシステム、他社の代行で培ったノウハウなどを使って、自社の代行もこなしてもらえます。リスク回避の面でも安心です。
人手不足が解消できる

採用などにコストや手間、時間をかけることなく、人手不足が解消できるのもアウトソーシングのメリットです。
必要なサポートを必要な時だけ受けられるので、ムダに常時人材を確保しておく必要がありません。コストをかけて採用しても定着しないと悩んだり、急な退職に慌てたりすることもありません。
労務管理なども不要である

中小企業にとって、従業員の雇用で発生する労務管理も意外に大きな負担です。複雑な給与計算や社会保険料の計算、年末調整などの手続きなど、時間のかかる作業がいくつもあります。
これらを専門業者に任せれば、自社の人材は本業やより高度な業務に集中でき、経営にもプラスに働きます。
事務代行サービスを利用するデメリット

事務代行には、デメリットに感じる点もあります。あらかじめ把握しておきましょう。
- 契約外の仕事はできない
- コミュニケーションがとりにくい
- 自社にノウハウが残らない
- 委託内容によりコスト高になる
- セキュリティリスクがゼロではない
それぞれ説明します。
契約外の仕事はできない

外部業者に事務を委託する場合、まずは「何を委託するか」を明確にして契約を結ぶ必要があります。契約開始後に、やってもらいたい仕事が契約外だとわかれば、追加代金を払うなどして依頼しなくてはなりません。
自社の従業員のように、担当が多少違っても「急ぎだから」などと都合よく頼めるわけではありません。
コミュニケーションがとりにくい
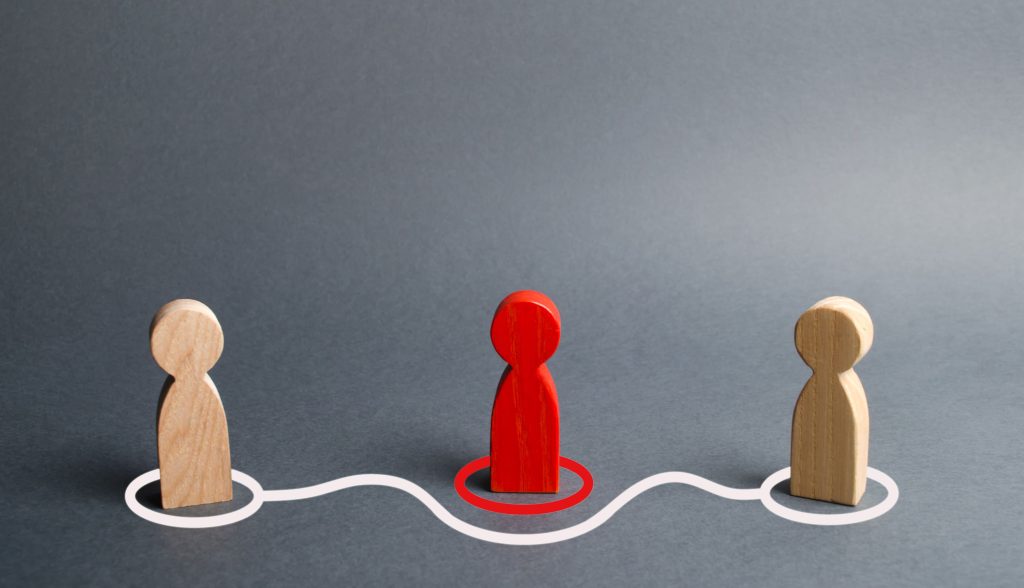
事務代行サービスの多くは、オンラインでのやり取りで完結します。そのため、物理的な距離によるコミュニケーションの取りにくさを感じることもあります。
目の前にいるわけでないため、「今すぐ頼みたい」「説明しながらすぐに対応してもらいたい」という場合にもタイムラグが生じ、もどかしい思いをするかもしれません。
自社にノウハウが残らない
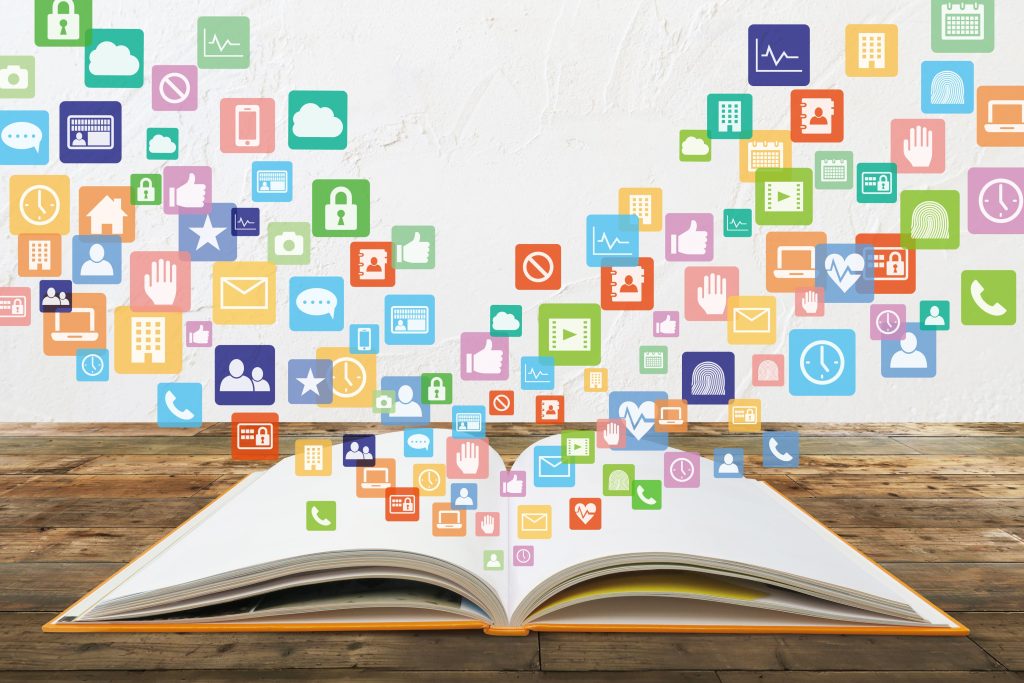
業務を代行してもらい、コストや手間が省ける代わりに、自社では知識やノウハウが残りません。
自社に「最新の状況がわかる人」がいなくなること、事務作業に関しては社員の成長が見込めないことがデメリットとなり得ます。
委託内容によりコスト高になる

事務代行の大きなメリットがコストの削減ですが、委託先の業者の料金設定や、委託する業務範囲などによっては、人を雇うのと変わらない、場合によってはそれ以上のコストがかかる恐れがあります。
必要な業務だけを委託する、まずは一部の業務だけを委託するなどして調整する必要もあるでしょう。
セキュリティリスクがゼロではない

代行業者は、複数のクライアントの業務を請け負います。そのため、セキュリティ対策を万全にしていることがほとんどですが、中にはそうでない業者がいる恐れも。また、いくらセキュリティ対策をしていても、リスクはゼロにはなりません。
事務では会社の機密事項も扱うため、なるべくセキュリティ対策のしっかりした業者を選びたいものです。
自社に合った事務代行サービスの選び方

メリットを最大限に、デメリットを最小限にするには、どのように業者を選べばいいのでしょうか。押さえておきたいポイントは次の4つです。
- まずは自社のニーズを洗い出す
- 各業者のサービス内容を把握する
- セキュリティ対策を確認する
- 実績や利用者レビューを参考にする
それぞれ説明します。
まずは自社のニーズを洗い出す
数ある業者の数あるプランの中から、自社に最適なサービスを選ぶには、自社のニーズを明らかにする必要があります。
現状の事務作業を紙に書きだすなどして可視化し、どの作業に時間がかかるのか、負担が大きいのかを洗い出しましょう。負担がかかる一部を委託するべきか、すべてを委託するか、といった判断もしやすくなります。
コスト減のつもりがコスト増にならないよう、予算も決めておくことをおすすめします。
各業者のサービス内容を把握する
事務代行と一口に言っても、各社のサービス内容や料金はさまざまです。同じ「経理事務」でも、たとえば給与計算は基本料金に含まれず追加料金がかかる、といったケースも多いです。
「当然やってもらえると思っていた」「追加料金が必要なら別の業者の方が安かった」などと後悔しないために、サービス内容は必ず見ておきましょう。
セキュリティ対策を確認する
事務代行サービス業者の選定時には、セキュリティ対策についても必ず確認してください。「業種柄セキュリティは当然しっかりしているだろう」と決め込むのは危険です。
「しっかりしているかどうか」を聞くのではなく、「どんなセキュリティ対策をしているか」の具体的な回答を聞いて判断してください。
実績や利用者の感想を参考にする
利用前に業者の良し悪しを判断するのは難しいですが、公式サイトに実績や利用者の感想が掲載されているなら目を通しておくのがおすすめです。
自社と同じ業界・業種のクライアントがいれば、委託がよりスムーズに行く可能性があります。他業界でも、他社がどのような利用の仕方をしているのかなども参考にするとよいでしょう。
【業種別】事務代行サービスの活用事例
最後に、事務代行サービスの活用事例を4つ、業種別に紹介します。
中規模建設会社の活用例

| 課題 | ・事務職員の人数が足りず、書類作成やデータ入力業務が滞りがち ・事務担当が高齢のため、自社ではITツールの導入も難しく非効率な状態 |
|---|---|
| 対策 | ・書類作成やデータ入力、電話対応などを事務代行サービスに委託 ・ITツールを活用した業務効率化のサポートを受ける |
| 効果 | ・事務処理のスピードが向上、業務効率化に成功 ・ITツールの活用で職員にも自信が生まれ、仕事への意欲も高まった |
ITツールを活用すれば業務効率化になるとわかっていても、「慣れない」「難しそう」と二の足を踏んでいるケースは多いものです。そんな場合にも、事務代行が役に立ちます。
小規模ECサイト運営会社の活用例

| 課題 | ・顧客対応や受注処理に追われ、商品企画やマーケティングの時間が取れない ・繁忙期の残業や、顧客対応のストレスが大きな負担となっている |
|---|---|
| 対策 | ・受注処理、在庫管理、顧客対応を事務代行に委託 ・繁忙期のみ、追加でデータ入力や梱包・発送作業も委託 |
| 効果 | ・商品企画などのコア業務に時間を避けるようになり、売上アップにつながった ・従業員の残業やストレスが減り、仕事の満足度が向上した |
事業のコアと呼べる部分(このケースでは商品企画やマーケティング)に注力できないことは、会社にとって大きなリスクです。事務代行でなるべく負担を減らし、売上アップにつなげましょう。
IT系スタートアップ企業の活用例

| 課題 | ・少人数で始めたため、バックオフィスまで手が回らない ・労務管理などの法が関わる専門知識がなく、コンプライアンスの不安もある |
|---|---|
| 対策 | ・記帳や請求書発行、給与計算や社保険の手続きなどを事務代行に委託 |
| 効果 | ・事業成長に直結する行動に専念できるようになった ・税理士などの専門家と連携した代行業者の活用で、法令遵守やリスクへの不安も払拭できた |
事務代行業者には、税理士などの専門家と提携しているところも数多くあります。
法令に関わることは、やはり専門家のサポートを受けるのが一番の方法。ひんぱんに行われる法改正に対応するには、常に最新情報をキャッチし、自社に必要な対応を速やかにしなくてはなりません。
士業事務所の場合

| 課題 | ・専門的な業務に集中したいが、顧客対応や事務作業に時間がかかる ・繁忙期と閑散期の業務量の差が激しく、人を雇うのは非効率となる |
|---|---|
| 対策 | ・顧客からの問い合わせ、書類作成、データ入力などを事務代行に委託 ・繁忙期のみ、追加で専門業務のアシスタント(資格不要の作業)も依頼 |
| 効果 | ・専門業務に集中できるようになり、顧客満足度も向上した ・ムダな人件費を使わずに、業務量の変化に対応できるようになった |
年間を通じて人手が足りないわけではなく、不要な閑散期もある…。こんな場合にも、必要な時だけ依頼ができる事務代行業者の活用が効率的です。
自社に合った事務代行でコア業務に専念しよう

事務代行は、総務や経理、人事などのバックオフィス業務を代行してくれるサービス。活用すれば、人手不足など自社の課題解決につながります。
とはいえ、どの業者もサービス範囲や料金、セキュリティ対策などは異なるため注意も必要です。
最も大切なのは、自社に合ったサービスを選んで利用することです。まずはニーズを明確にし、その上で希望や予算に合う業者を選びましょう。
当社「Bricks&UKアウトソーシング」は、税理士法人を母体に持つ経理アウトソーシング会社です。経理以外の事務代行サービスの実績もありますので、ぜひお気軽にご相談ください。