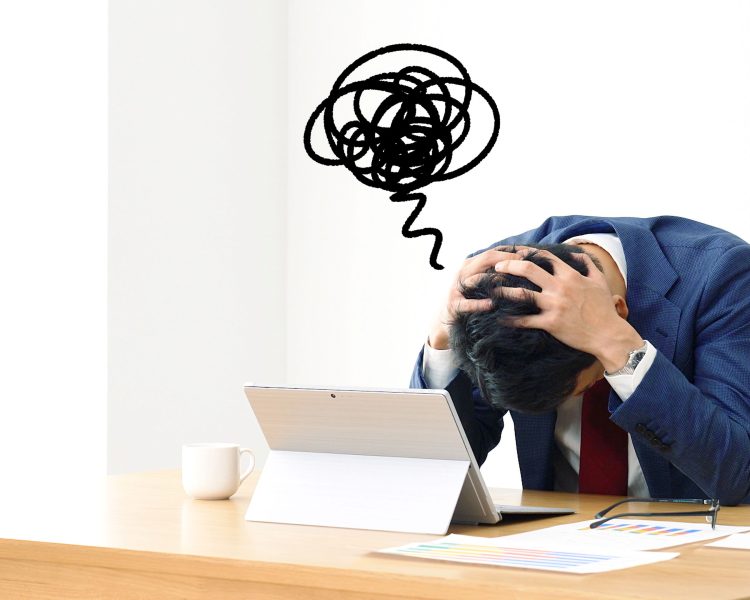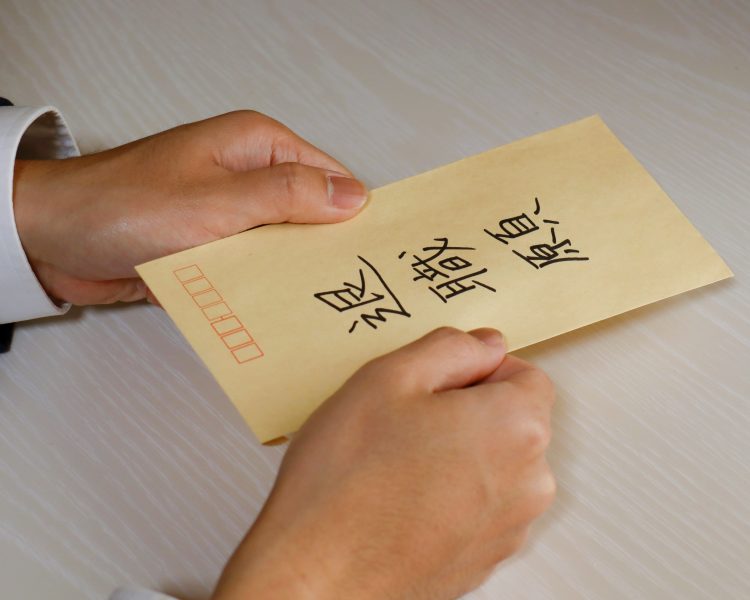給与計算間違いが多い会社のリスクとは?ミスへの対処と予防策を解説2025.04.07

従業員の給与計算を間違え、本人からの指摘で発覚…実はどの会社でも起きうることで、特に珍しいことでもありません。
しかし、給与計算のミスは従業員からの信頼を損ねるほか、未払い分があったとなれば法律にも関わります。「ミスは誰にでもある」と甘く見て間違いを繰り返すことは許されません。
今回は、給与の計算間違いが会社にもたらすリスクや、間違いが起こる原因、起きてしまった場合の対処法から予防策まで解説します。
【この記事の監修者】 株式会社Bricks&UK Outsourcing業務コンサルタント
経理の業務設計・運用に優れたコンサルタントが、効率的で正確な業務請負いをお約束します。
目次
給与計算の間違いが会社にもたらすリスク
会社が従業員の給与を間違えて計算することには、次のようなリスクがあります。
従業員の信用を失う
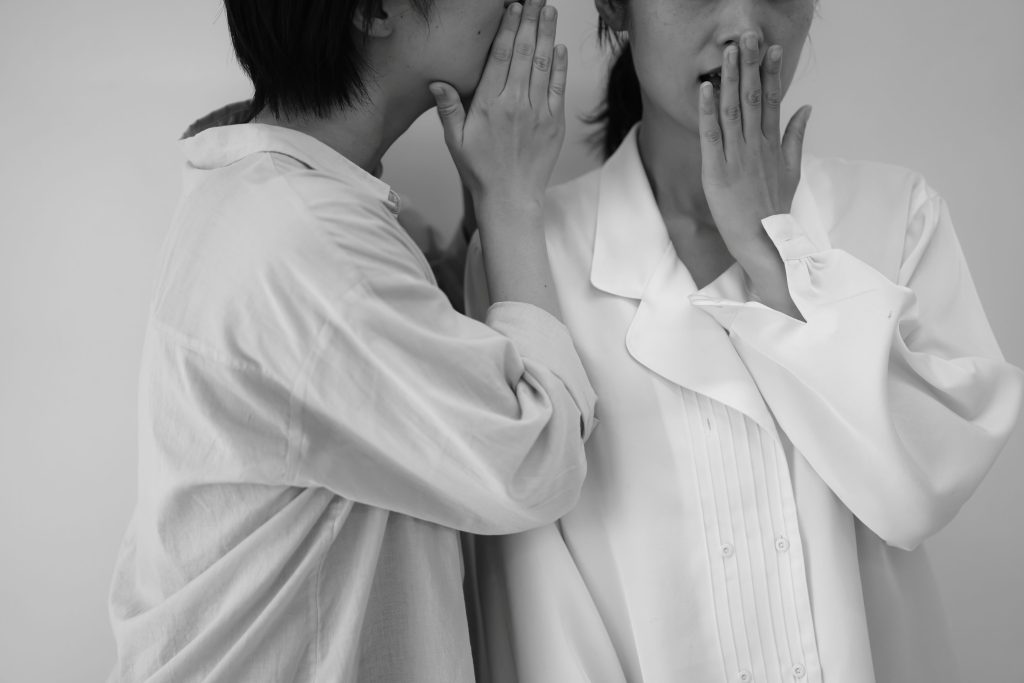
従業員は通常、会社が給与計算を間違えるとは予想していません。そのため、間違いに気づいた際は大いに驚きます。
そして、「自分が気づかなかったらどうなっていたのか」「これまでも間違えていたのでは?」「まさか確信犯的?」などと、会社への不信感を持ってしまいます。
多くの場合、自分の胸だけにとどめず、周りの同僚などにも話します。そのため、他の従業員からの信用もなくすことになります。
労働基準法に違反する

「不足分を後から払えばいいだろう」「少し計算を間違えただけで問題ない」と思いがちです。
しかし、計算ミスにより給与が本来支払うべき額に足りていなかった場合、故意でなくても労基法違反となる恐れがあります。
というのも、給与支払いには、労働基準法に「賃金支払いの5原則」と呼ばれる規定があるからです。その内容は次のとおりです。
- 通貨で支払う
- 労働者に直接支払う
- 全額を支払う
- 毎月1回以上支払う
- 一定の期日を定めて支払う
金額に不足がある場合、上の「全額を支払う」規定に反します。
ここでいう「全額を」には「一括で」という意味も含みます。不足分を後から支払ったとしても、それは分割払いに等しく、全額を支払うことになりません。
過払い時の返還トラブル

給与の計算を間違え、多く支払ってしまうケースもあります。その場合、受け取った従業員の側には返す義務があり、会社には「不当利得返還請求権」、つまり返してもらう権利があります。
しかし、中には当の従業員が返還に応じず、トラブルになる事例もあります。退職後に発覚した場合や別の退職トラブルがあった場合には特に、回収できない可能性も。
また、過払い額が大きい場合には、社会保険料や所得税、住民税などの計算にも関わってくるため、後の処理が複雑になります。
給与計算の間違いが発生しがちなケース

一般に過去の事例を見ると、給与計算の間違いは次のような時に多く発生しています。
- 昇給
- 降格処分に伴う減給
- 各種手当額の変更
(役職手当、交通費、資格手当など) - 時間外労働の計算
(割増賃金の有無など) - 従業員の異動
- 扶養家族の増減
- 介護保険料の徴収開始
(40歳になる誕生日の前の月) - 月途中の退職時の日割り計算
- 月途中の退職時の保険料控除
(月途中の場合は本来控除なし) - 社会保険制度の改定
間違いが起こりやすいのは、給与額を決める何らかの要素が変更となった時です。
単なる計算ミスというよりは、変更すべきことに気づかず従前の給与をそのまま支払う、控除すべきものを控除し忘れた(もしくは逆)、などがよくあるパターンです。
給与計算に間違いが起こる原因

給与計算の間違いは、次のようなことが原因で起こります。
- 担当者の経験・知識不足
- 多忙によるケアレスミス
- 複雑な給与形態
- 多様な働き方への対応
- 手作業による計算ミス、入力ミス
- 給与計算ソフトの設定ミス
- 社内での最新情報の共有もれ
それぞれ解説します。
担当者の経験・知識不足
担当者に給与計算についての知識・経験が足りない場合、給与計算を間違えてしまいがちです。
特に中小企業の場合、後任者への十分な引き継ぎなく前任者が退職したり、経理未経験に近い人を雇って給与計算を任せたりするケースも少なくありません。
多忙によるケアレスミス
給与計算は、毎月限られた期間に行う必要があります。締め日以降、出勤簿やタイムカードを集計し、申請もれや打刻もれ、間違いなどがあれば、まずはその対処から始めなくてはなりません。
1人ひとりの給与を正しく計算する作業は時間がかかる上、給与計算以外にもやることは当然あります。作業の中断を余儀なくされるなど、間違いが起こりやすい状況です。
複雑な給与形態
営業社員は年俸制、事務職は月給制など、部署などによって給与形態が異なっているのも、間違いを生む原因の1つです。
また、計算方法に「固定給+残業代」や「固定給+歩合給」など複数の方法を取り入れている場合にも、対応が複雑化し、ミスが起きやすくなります。
多様な働き方への対応
働き方改革の流れで、従業員の働き方も多様化しています。勤務時間や日数が人によってバラバラだと、間違いも起こりやすくなります。
これについては、「柔軟な働き方」を認める制度の義務化などを受け、今後さらに複雑化する可能性があります。
手作業による計算ミス、入力ミス
給与計算がすべて手作業であることも、計算間違いを起こす原因です。
手作業で行うには、従業員1人ひとりの勤怠、扶養家族などの情報の取りまとめから、たとえば昇給による基本給の変更、転居に伴う交通費の変更など、さまざまな作業があります。
期限もある中、手間も時間もかかる手作業では、ミスが起きても不思議ではありません。
給与計算ソフトの設定ミス
給与計算ソフトが導入されていても、ミスは起こり得ます。
給与計算ソフトを使うのにも、従業員の基本情報や給与情報などは手入力で行い、初期設定をする必要があります。
この登録設定の内容を間違えてしまえば、間違った額で自動計算されてしまいます。
社内の情報共有もれ
他部署からの必要情報、たとえば昇給や役職の変更、扶養家族増加といった情報が経理に届かないと、給与計算も正しくできません。
本人からの届出を直属の上司が持ったまま、あるいは届出の制度が確立されていないケースもあります。休日出勤した分の集計もれなどもよくあることです。
税制改正など給与計算に関わる社会制度の変更情報も、常にキャッチして担当者に共有しなくてはなりません。
給与計算の間違いが見つかるきっかけとは

給与計算を間違えて支払ったと判明するきっかけには、いくつかのケースがあります。
- 従業員本人からの問い合わせ
- 税務調査
- 社会保険の算定基礎届の提出時
- 年末調整時
- 会計監査や内部監査
順に見ていきましょう。
従業員本人からの問い合わせ
多くの場合、給与計算の間違いは従業員本人からの問い合わせで発覚します。昇給や交通費の変更などは本人が一番理解しており、少額でも気づきやすいからです。
給料日すぐに気づかれるケースもあれば、退職後などに気づいてしばらく経ってから問い合わせてくるケースもあります。
税務調査
税務署による税務調査で、源泉徴収の額や社会保険料の計算が間違っていると指摘されるケースがあります。
本来納めるべき税金の額と異なれば、不足分の税額はもちろん、過少申告加算税や延滞税などの支払いも必要となります。場合によっては、従業員の所得税にも影響が出ます。
社会保険の算定基礎届の提出時
毎月7月に提出する給与の算定基礎届は、支払った給与の額をもとに社会保険料を計算するものです。
そのため、この算定基礎届を出す際に、過去の支払額の間違いに気づくことがあります。
過去データなどとの照合の上、社会保険事務所から指摘を受ける可能性もあります。
年末調整時
年末調整の時点で、年間の給与額や源泉徴収額が間違っていると判明することもあります。
たとえば、従業員に渡す源泉徴収票の金額が、会社が管理している記録の数字と違う、といったケースです。
会計監査や内部監査
会計監査や内部監査でも、給与計算に間違いがあれば指摘されます。
監査では、給与計算を行う担当者へのヒアリングや、給与計算ソフトの内容確認、帳簿の確認を行います。
給与規定と給与計算プロセスに矛盾がないかなども確認して、給与が正しく支払われる体制かどうかを調べます。
給与に計算間違いが発生した際の対処法

発覚のきっかけが何であれ、給与計算が間違っていればすぐに対処する必要があります。会社が取るべき対応は次のとおりです。
- 1)当人への速やかな謝罪とていねいな説明
- 2)過不足金の調整
- 3)再発防止策の検討・実施
順に見ていきましょう。
1)当人への速やかな謝罪とていねいな説明
給与計算の間違いに気づいたら、早急に当の従業員に連絡し、事実を伝えて謝罪します。
言い訳や責任転嫁をせず、会社側の間違いを率直に認めて速やかに謝罪することが、社員の不信感を軽減させるポイントです。
間違いの原因や今後の予防策などについて、当人が納得するまでていねいに説明し、過不足分の調整方法・時期も伝えます。
給与額などの情報は、ごく個人的なものです。プライバシー侵害などを避けるため、基本的に社内への公表は不要です。
しかし、対象となる従業員が多数の場合、もしくは、システムエラーなどが原因で全体に影響を及ぼす可能性がある場合には、社内全体への公表も検討する必要があります。
2)過不足金の調整
計算間違いで少なく支払った場合、不足分をできるだけ早く支給します。希望があれば現金での手渡しなども検討する必要がありますが、その際も記録はしっかり残しておきましょう。
過払いだった場合には、返還の方法を当人と相談して決めましょう。返還を拒否されるなどのトラブルを避けるべく、より慎重に対処する必要があります。
不足分の支払いを翌月に持ち越すと、労基法違反につながります。
当人が希望する場合など、例外的な措置も可能ですが、両者が合意済みであると書面などに残すのが得策です。
3)再発防止策の検討・実施
再発防止にはまず、なぜ給与計算に間違いが起きたのか、その原因を追究する必要があります。
担当者のケアレスミスだった場合も、当人がミスをした背景、たとえば労働環境に問題がないか、間違えやすい作業プロセスになっていないかなどを、多角的に分析してください。
突き止めた原因にもとづいて、社内で再発防止策を検討、なるべく早く実行に移します。
再発防止策の作成時は、コンプライアンスにも留意する必要があります。専門知識も必要なため、社会保険労務士など社外の専門家に相談するのがおすすめです。
給与計算の間違いをなくすための予防策

給与計算に間違いが起こる原因は複数あるので、複数の対策が必要です。たとえば次のような対策が効果的です。
チェック体制の強化
給与計算間違いの原因の多くは、確認をしっかりすることで防げます。
チェック体制はあってもリストがないなら、チェックリストを作り、確認しながら作業を進めます。担当者が1人の場合でも、上司などがダブルチェックを行う体制を作りましょう。
勤怠管理システムの導入
手入力が必要なタイムカードなどを利用している場合は、勤怠管理システムを導入することで計算間違いを防ぐことができます。
従業員はパソコンで打刻、あるいは社員証をカードリーダーにかざすなどして出退勤を記録するだけ。残業などを含め、勤怠データが自動集計されます。
給与計算ソフトの導入
Excelなどを使って給与計算をしているなら、給与計算ソフトの導入を検討しましょう。特にクラウド型のソフトを使えば、何もしなくても常に最新の法令に基づいた状態で使用できます。
勤怠管理システムと連携させれば、残業時間や社会保険料などの計算も自動、給与明細書の発行なども自動です。年末調整の作業や帳簿の作成時にも効率よく作業できます。
情報共有体制の見直し
部署間の情報共有がスムーズにいかないことも、給与計算の間違いを生みます。従業員の給与額に関して変更があった場合に、リアルタイムで情報共有ができる体制を整えましょう。
報告すべき事案とは何か、発生した場合はどうするか、などの社内ルールを決め、関係者全員に周知します。共有にはソフトウェアやアプリを活用しましょう。
専門家への相談
法令や社会制度に適応するには、常に新たな情報をキャッチすること、その情報を正しく理解し対処することが必要です。自社で対応が難しい場合には、社会保険労務士などの専門家に相談するのがおすすめです。
ソフトウェアやツールの導入、業務プロセスの見直しなどには、コンサルタントや専門業者への相談も1つの方法です。
経理・給与計算代行サービスの活用
外部業者には、経理や給与計算などの業務に特化した代行サービスもあります。給与計算を代行業者に委託すれば、専門のスタッフが担当するためミスが防げます。
委託には費用もかかりますが、人を1人雇うよりコストを節約できる傾向にあります。従業員の負担軽減や業務の効率化など、プラスアルファのメリットも大いに期待できます。
当社のクライアントでも、アウトソーシングすることで給与振込に関するミスがなくなった、という喜びの声をいくつかいただいています。一例を紹介しているので見て、見てみてください。
給与計算の間違いはツールや代行サービスで防止しよう

人が行う給与計算には、どうしてもミスが起こりがち。ですが、単なる計算ミスでも労基法違反につながるため、十分な注意が必要です。
間違いが発覚したら、当人への即時対応はもちろん、再発防止に努めなくてはなりません。
自社の状況によって、勤怠管理ソフトや給与計算ソフトを導入する、社外の専門家に相談する、代行サービスに委託するなどの策を取りましょう。
当社「Bricks&UKアウトソーシング」は、中小企業の経営に強い税理士法人を母体とした、経理代行サービス会社です。
給与計算は当社では行っておりませんが、グループ企業である「社会保険労務士事務所Bricks&UK」が代行いたします。
当社では、連携して給与振込などを承れますし、業務プロセス改善のご提案も皆様からご好評をいただいています。ぜひお気軽にお問い合わせください。